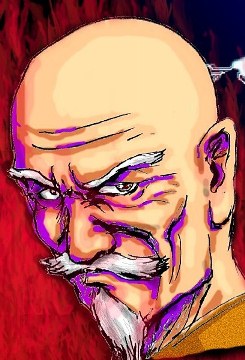皆様、お待たせしました。論文感想の時間です(←待ってないか・爆)
肥前国には本来一つしかないはずの一宮が二つある。
與止日女神社(河上社)と千栗八幡宮の二つだ。
一宮争いをしていた両神社だが、未だ結論が出ていないのであろう。
全国一宮一覧では、シッカリ両方載ってます( ̄ω ̄A;アセアセ
與止日女神社(河上社)と千栗八幡宮の二つだ。
一宮争いをしていた両神社だが、未だ結論が出ていないのであろう。
全国一宮一覧では、シッカリ両方載ってます( ̄ω ̄A;アセアセ
論文は専門的な話やココ**論文参照ねってのが、チョコチョコあって参照論文未読のシオはポカーン。
(もっとも更に戦国から離れた専門的な論文になるので、読んでも判らない可能性大)
ま、とりあえず千栗八幡宮が川上社に圧倒された経緯は大体つかめたので、忘れない内に感想アップします^^
(もっとも更に戦国から離れた専門的な論文になるので、読んでも判らない可能性大)
ま、とりあえず千栗八幡宮が川上社に圧倒された経緯は大体つかめたので、忘れない内に感想アップします^^
千栗八幡宮は創立は別にして鎌倉中期には、宇佐八幡宮の九州五所・別宮の一つだったことが「旧記雑録前編(島津史料)」に記載されているそうです。
で、平安期から鎌倉中期にかけて千栗八幡宮が「肥前国一宮」として存在してたことが窺える文書があるとのこと。
で、平安期から鎌倉中期にかけて千栗八幡宮が「肥前国一宮」として存在してたことが窺える文書があるとのこと。
ところが1309年に宇佐宮と弥勒寺が大火により悉く灰塵に帰した事から、宇佐八幡宮の衰微が始まる。
で、その余波で宇佐八幡別宮だった千栗八幡宮も衰退。
代わって河上社が肥前国一宮の神号を唱え台頭し始めた。
・・・・って、それじゃ自称・・・(._+ )☆\(-.-メ)オイオイ
で、その余波で宇佐八幡別宮だった千栗八幡宮も衰退。
代わって河上社が肥前国一宮の神号を唱え台頭し始めた。
・・・・って、それじゃ自称・・・(._+ )☆\(-.-メ)オイオイ
一宮争いで決着がつかない理由で一番大きいのは、千栗八幡宮側に中世(室町~戦国まで)の文書がゴッソリないことです
ガ━━━(゚ロ゚;)━━ン!! ガ━━━(゚ロ゚;)━━ン!! ガ━━━(゚ロ゚;)━━ン!!一番、肝心な時代がぁぁぁぁ!
あ、別段陰謀じゃないです。何度も戦火にあって焼失=消失したんです。 (゜-Å) ホロリ
戦火にあってるのは河上社も同じで、やっぱり中世の文書量が前後と比較するとガクンと減ってます。
そうだ、基本的な事なんだけど現代人はピンと来ないので書いときますね。
明治以前は神仏習合ですので、神社には別院としての寺院がセットで付随してました。
カードで言えば表が神社で、引っくり返すと寺院。だから座主が両方を兼務するのは普通^^b
河上社の別院が実相院。
千栗八幡宮の別院が妙覚院。
おそらく往時の千栗妙覚院では、河上実相院の「如法経会」に匹敵する仏事が盛大に催されてたはず・・
と論文に書いてるけど、シオもそう思うな~だってでないと不自然なんだもん^^
明治以前は神仏習合ですので、神社には別院としての寺院がセットで付随してました。
カードで言えば表が神社で、引っくり返すと寺院。だから座主が両方を兼務するのは普通^^b
河上社の別院が実相院。
千栗八幡宮の別院が妙覚院。
おそらく往時の千栗妙覚院では、河上実相院の「如法経会」に匹敵する仏事が盛大に催されてたはず・・
と論文に書いてるけど、シオもそう思うな~だってでないと不自然なんだもん^^
論文では薩摩国で起きた一宮争いを参照として紹介してるんだが、さっぱりワカラン,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!
で、千栗八幡宮衰微の決定的要因として、肥前国が東大寺造営料国になった事をあげてるけど、
多分、金銭的な圧迫(相応負担)があったって事なんだろうけど、それが千栗八幡宮にとって何がどう大変なのか具体的な事が書いてないので是もイマイチワカラン(-ω-;)ウーン
で、千栗八幡宮衰微の決定的要因として、肥前国が東大寺造営料国になった事をあげてるけど、
多分、金銭的な圧迫(相応負担)があったって事なんだろうけど、それが千栗八幡宮にとって何がどう大変なのか具体的な事が書いてないので是もイマイチワカラン(-ω-;)ウーン
とにかく河上社を一宮とすべくプッシュしたのは、河上社11代目座主・辮髪だったそうだ。
11代目座主は鎌倉北条得宗家の専制体制確立と元寇という国家の大事に便乗。
「異国征伐の軍神=河上社祭神」であると強調し、一宮にすべく神格を押し上げたわけです。
11代目座主は鎌倉北条得宗家の専制体制確立と元寇という国家の大事に便乗。
「異国征伐の軍神=河上社祭神」であると強調し、一宮にすべく神格を押し上げたわけです。
これには河上社造営のために何としても予算確保したいって気持ちが嵩じての事だったようです。
肥前国が東大寺造営料国になった余波が河上社にも及んで、由緒ある神社には定期的にある造替が伸び伸び後回しにされてたから^^;
肥前国が東大寺造営料国になった余波が河上社にも及んで、由緒ある神社には定期的にある造替が伸び伸び後回しにされてたから^^;
中世の文書~川上社激減・千栗八幡宮消失なので、ここから先は論文にないシオ推測です。
上記の経緯だけだと、さも河上社が独断で自称したみたいで、すぐ一宮争いに決着つきそうなものですが、そうは問屋が卸さない。
その後継者となったのが河上社の大宮司となった肥前千葉氏。
上記の経緯だけだと、さも河上社が独断で自称したみたいで、すぐ一宮争いに決着つきそうなものですが、そうは問屋が卸さない。
それは国衙(政庁)機能を有してた河上社が現実に肥前国一宮という待遇を受けてた・・・はずだからです
河上社の有する国衙機能を利用して肥前を支配するスタイルを完成させたのが、稀代の名将と謳われた九州探題・今川了俊です。その後継者となったのが河上社の大宮司となった肥前千葉氏。
彼等、肥前国の支配者にとって河上社より権威ある神社仏閣があっては都合が悪いはずで、あくまでも肥前国一宮は河上社でなければならない。
中世の千栗八幡宮は何らかの圧力を受けてたと・・・・思うんだが、それを証明する文書がない件~(_´Д`)アイーン
とにかく、その時代の政治事情によって一宮の変遷があったため、どっちが一宮と一概に決めつけられなくなっちゃってるんです( ̄ω ̄A;アセアセ
中世の千栗八幡宮は何らかの圧力を受けてたと・・・・思うんだが、それを証明する文書がない件~(_´Д`)アイーン
とにかく、その時代の政治事情によって一宮の変遷があったため、どっちが一宮と一概に決めつけられなくなっちゃってるんです( ̄ω ̄A;アセアセ
>河上実相院の「如法経会」に匹敵する仏事
ですが、論文ではウッスラと窺える話が紹介されてました。
一宮争いで千栗八幡宮側では
もともとは修行僧が行ってたのが民衆にも伝わりました(省略して行脚は6ヶ所も可)。
今じゃ殆ど見かけないですが、持ち物・装束やカンパで旅するスタイルは四国巡礼お遍路さんと、ほぼ同じです。
往時の千栗八幡宮では法華経に因んだ修行僧が集まる一大イベントが定期的にあったんじゃないでしょうか。
ですが、論文ではウッスラと窺える話が紹介されてました。
一宮争いで千栗八幡宮側では
「一宮社格の神号論拠を往古より今に至るまで千栗山が肥前国における廻国聖六十六部法華経奉納所であった事実を強調している点である (「」内、論文よりママ引用)」廻国聖とは法華経を六十六部書写して決められた霊場(奉納所=寺院)に納めるために行脚する事でして、
もともとは修行僧が行ってたのが民衆にも伝わりました(省略して行脚は6ヶ所も可)。
今じゃ殆ど見かけないですが、持ち物・装束やカンパで旅するスタイルは四国巡礼お遍路さんと、ほぼ同じです。
往時の千栗八幡宮では法華経に因んだ修行僧が集まる一大イベントが定期的にあったんじゃないでしょうか。
論文では(廻国聖が民間信仰として広く伝わったお蔭で)千栗八幡宮は衰亡しつつも民間信仰の聖地として命脈を保持しつづけた事は注目に値いする~という感じで結んでました。
期待してた中世(室町~戦国)部分がなかったのはショックでしたが、こればかりは仕方ないですね。
川上社が「肥前国一宮として台頭する」のと、
肥前千葉氏が肥前に土着し台頭するのは、密接にリンクしてます。
肥前千葉氏が肥前に土着し台頭するのは、密接にリンクしてます。
それは千栗八幡宮衰亡の歴史へと繋がることなんです。
千栗八幡宮に中世の文書があれば、探題・今川了俊との関係も含めて、もっと色々見えてくるんだけど~~残念!!
千栗八幡宮に中世の文書があれば、探題・今川了俊との関係も含めて、もっと色々見えてくるんだけど~~残念!!
此処まで読んで下さった奇特な方・・・ありがとうございます^^
長くなるんで他の論文感想は、そのうちまたアップします^^
末筆ですが論文提供者様に心より感謝を述べて感想を終わりますm(__)m
長くなるんで他の論文感想は、そのうちまたアップします^^
末筆ですが論文提供者様に心より感謝を述べて感想を終わりますm(__)m