国人領主が被官から自立した勢力に成長(戦国大名化)するには、「津(港)」が必要というのは、あくまでも肥前の場合です。
例えば甲斐国のような山国では適用しないと思います。
肥前における物資流通で河川を使った舟便は欠かせません。
何故なら、満干潮による河川逆流現象で浸水被害が必ずあるため「安定した陸の輸送」が困難だったからです。
逆を言うと肥前において一定の勢力がある国人領主は、物資流通の要である河川港か河口港を何らか形で保持してたんじゃないでしょうか。
龍造寺初期台頭時代は、位置的に八田江川流域にあった八田橋の津を利用してたと推測出来ます。
剛忠(家兼)の代で勢力拡大し、少弐氏が開港した今宿・今津・相応津は龍造寺が支配下に治めた・・・と思う。
思う~~になるのは、剛忠(家兼)が兵馬を用いず政略結婚などで「周囲の豪族を手なずける」という長いスパンをかけたからです。
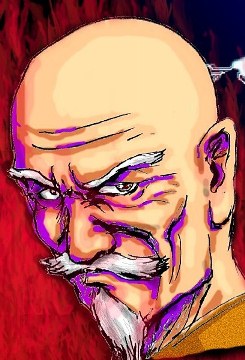 剛忠(家兼)イメージ画像
剛忠(家兼)イメージ画像剛忠(家兼)という人物は、とても強かで、凄く慎重で、相当に用心深い。
自分の調べた範囲ですが、剛忠(家兼)の方から大内氏に接触した事はないでしょう。
(和睦の仲介を「大内の方から」頼まれた事はある)
でも少弐の資産だった今宿・今津・相応津(周辺領地含む)を支配下に治める行為は、龍造寺が「主君に対する重大な裏切り」を働いた証になります。
剛忠(家兼)も、それを判ってるから少弐に気付かれないように、ゆっくり、じんわりと勢力を広げてた。
勢力拡大の分岐点は、鍋島様の赤熊武者が活躍し龍造寺の武勇を肥前中に轟かせた「田手畷の戦い」ではないでしょうか。
相応津・今津を支配したのは、肥前石井氏が龍造寺家臣になった頃(田手畷合戦以降)になると思います。
剛忠(家兼)は肥前石井氏に海岸警固を命じてます。
当然、警固対象には河口港である今津と相応津が含まれます。
何故なら肥前石井氏の飯盛城は、今津と相応津の中間地点に位置してるからです。
今宿が龍造寺勢力圏に入ったのは、シオ推測では1536年の少弐資元自害以降。
この時に蓮池城の肥前小田氏が「御父上(資元)が自害になったのは、龍造寺が裏切ったから」と、少弐冬尚に讒言してるからです。
佐賀江川流域が勢力圏だった肥前小田氏にとっても、今宿は喉から手が出るほど欲しかった河川港だったはず。
ショートカット工事前の佐賀江川は、物凄く蛇行してて浸水被害も広範囲。
戦国期は大きな津を作るほどの治水土木技術が未だ追いついてません。
治水の神と称えられた成富茂安ですら「佐賀江川の蛇行には手をつけるな」と遺言してたほどです^^;
(手をつけて失敗したら元に戻せない)
従って肥前小田氏は、佐賀江川と八田江川の分岐点である河川港・今宿に、物資流通ライフラインを依存してたでしょう。
今宿には商人たちが移り住み後世の繁栄を予測させる商業圏が育ちつつありました。
運上金とかの利権が絡んできまつよね・・・( ̄ko ̄)
肥前小田氏と龍造寺は、今宿の支配を巡るライバルだったのではないか?というのが自分の推測。
その肥前小田が龍造寺を讒言するって事は、今宿が龍造寺勢力圏に入って、経済的に肥前小田を脅かす危機が高まったからじゃないでしょうか。
少弐資元自害で少弐がゴタゴタ混乱してる頃なら、龍造寺が今宿をゲットする絶好のチャンスですよね(^ -)---☆Wink
神埼に拠点を移した少弐氏は佐嘉郡に目が行き届かなくなり、龍造寺の勢力拡大に対する認識が遅れたと思います。
気づいていても大内へ対抗する為には「龍造寺の武勇」が必要で、切り捨てる事が出来ませんでした。
ジレンマの果てに我慢の限界に達し、馬場頼周立案「龍造寺抹殺計画」が遂行されます。
 ロン様作成:少弐家紋ロゴ
ロン様作成:少弐家紋ロゴ剛忠(家兼)がリフォームした水ヶ江城は、クリークを利用しており5つあった館(曲輪)は、それぞれ独立してたそうです。
その為、5館全部を合わせた広さは30町(約3.3km)という広大さでした。( ゚д゚)ンマッ!!
無数にあるクリーク。広大な場所にある独立した各館。
火縄銃・大砲のない時代なら充分に「攻めづらい城」です。
少弐氏が剛忠(家兼)を裏切り水ヶ江城を囲んだ時に、万単位の兵力を揃えたのは、後世になったからの数の盛りじゃないでしょう。
この広さなら、そのくらい要ります~本館だけ囲むって都合良くいかないですもん~( ̄ω ̄A;アセアセ
それを思うと、少弐が有馬と組んだのも、万単位の軍勢が必要だったからだったのネー(*´・д・)(・д・`*)ネー
地形と城って密接な関係があるんですが、肥前は独特です。
パッと見は無防備そうに見える平城でも、戦国当時は城周囲がクリークや湿地帯で守られてて、敵が簡単に攻略できないように工夫されてるんです。
これは干拓・灌漑・護岸工事が終わった平成現代の地図からでは、イメージ出来ません。
戦国時代の海岸線・河川蛇行・逆流現象浸水被害の範囲・クリークの有無が予備知識として必要になります。
もちろん周辺にある山の標高とかも必要なのネー(*´・д・)(・д・`*)ネー
地理嫌いだったので初めは大変でしたが、今は楽しく地形を調べてます^^
末筆ですが、ブロ友様へ~水ヶ江城をリサーチするヒントをありがとうございました。
この場を借りて御礼申し上げますm(__)m
http://history.blogmura.com/his_sengoku/ にほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代